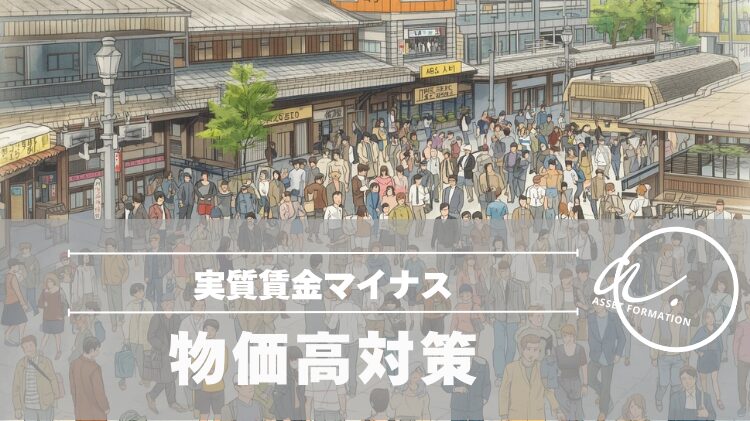【2025年最新版】NISAにおすすめのネット証券ランキング|投資初心者向け


この記事では以下の悩みを解決し、自分にあった証券会社を選ぶことができます。
投資初心者でNISAを始めたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
- NISAを始めたいけれど、証券会社が多すぎてどこを選べばいいか分からない
- 手数料やポイント制度など比較項目が多く、複雑すぎる
- アプリの使いやすさやサポート面が不安で、最初の一歩が踏み出せない
ネット証券はここ数年で急速に増え、それぞれが特色を打ち出しています。
しかし、何となく選んでしまうと「銘柄数が少なく投資の幅が狭い」「アプリが使いづらい」「ポイント還元が条件付きでほぼ使えない」などの失敗を招くことも。
NISA口座の証券会社変更には手間がかかるため、最初の選択が重要です。
私はFP資格を取得し家計を見直し、投資資金を捻出して4年で資産ゼロから1.5千万円以上を達成しました。
本記事では、筆者が実際に利用して得た経験に加え、オリコン顧客満足度ランキングや最新のNISA口座開設数データといった客観的な統計情報を徹底的に分析。
主観とデータの両面から検証することで、数あるネット証券の中から信頼性の高い証券会社だけを厳選してご紹介します。
ネット証券主要5社のNISA口座数や取扱銘柄数、株式売買手数料、ポイント制度、アプリの使いやすさなどを比較表で整理しています。
筆者おすすめの証券会社は「SBI証券」「楽天証券」です。
「SBI証券」「楽天証券」をおすすめする理由と初心者が選ぶ際の注意点や、総合力の高い証券会社を見極めるポイントを解説します。
この記事を読めば、初心者でも迷わず自分に合った証券会社を選び、NISAを活用した効率的な資産形成をすぐに始められるようになります。
失敗しない選び方で、安心して長く使える証券口座を手に入れましょう。
ネット証券を選ぶ前に知っておくべき3つのポイント

- NISA開設口座数
- 取扱商品の幅広さと手数料
- アプリや取引ツールの使いやすさ
はじめての証券会社選びは「安心感と分かりやすい」ことを第一条件にすると良いでしょう。
ネット証券NISA口座開設数比較(主要5社)
| 証券会社 | NISA口座開設数 (目安) | NISA含む全口座開設数 (目安) |
|---|---|---|
| SBI証券 | 約653万口座 (2025年6月末時点) | 約1,400万口座 (2025年3月末時点) |
| 楽天証券 | 約600万口座 (2024年12月末時点) | 約1,200万口座 (2025年3月末時点) |
| マネックス証券 | 情報なし (NISA口座数非公表) | 約270万口座 (2025年3月末時点) |
| 三菱UFJ eスマート証券 (旧auカブコム証券) | 情報なし (NISA口座数非公表) | 約180万口座 (2025年3月末時点) |
| 松井証券 | 情報なし (NISA口座数非公表) | 約165万口座 (2025年3月末時点) |
マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、松井証券はNISA口座数非公表となっています。
非公表の3社はSBI証券・楽天証券に、大きく水をあけられていることが、全口座数からも分かります。
口座数は規模の大きさですから、手数料・取扱商品数・使いやすやに関係してきます。
やっぱり、口座開設数の多い証券会社が安心できると思います。
初心者におすすめするネット証券比較表(主要5社)
次にNISAで買える投資信託の本数、株式の売買手数料をみていきましょう。
| 証券会社 | NISA つみたて投資枠 取扱本数 | NISA 成長投資枠 取扱本数 | 株式売買手数料 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 約270銘柄 | 約1,300銘柄 | 0円 (現物・信用ともに) |
| 楽天証券 | 約250銘柄 | 約1,300銘柄 | 0円 (現物・信用ともに) |
| 松井証券 | — (非公開) | — (非公開) | 0円 (50万円以下) |
| 三菱UFJ eスマート証券 (旧auカブコム証券) | 約260銘柄 (みんかぶ) | 約1,100銘柄 ( みんかぶ) | 0円 (25万円以下) |
| マネックス証券 | 約260銘柄 (みんかぶ) | 約1,200銘柄 (みんかぶ) | 0円 (現物・信用ともに) |
つみたて投資枠の取扱本数は1位SBI証券、2位マネックス証券・三菱UFJ eスマート証券
成長投資枠の取扱本数は1位SBI証券・楽天証券、3位マネックス証券
補足ポイント
・株式売買手数料とは
個別企業の株を売買する際に支払う必要があります。
取引が成立した金額に応じて、各証券会社の定めた手数料のことです。
将来的に個別企業の株を売買したいときに、手数料0円の証券会社を選んでおくと安心できますね。
「取引のしやすさ」満足度ランキング(オリコン調べ)

オリコンが実施したネット証券の利用者満足度調査において、「取引のしやすさ」に関するランキングは以下の通りです。
引用|オリコン顧客満足度ランキング
| 順位 | 証券会社 | 満足度スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 楽天証券 | 83.7 |
| 2位 | SBI証券 | 81.5 |
| 3位 | マネックス証券 | 80.5 |
| 4位 | 松井証券 | 78.7 |
| 7位 | 三菱UFJ eスマート証券 | 77.1 |
- 楽天証券が圧倒的1位(83.7点)
スマホアプリやサイトの操作性、注文のしやすさ、初心者にやさしいデザインなどが評価されており、「取引のしやすさ」で5年連続の1位を維持しています。 - SBI証券も僅差で2位(81.5点)
取引ミス防止の工夫やVポイント利用など、実用的な使いやすさが支持されています 。
楽天証券のスマホ画面では、余計な情報が少なく、資産状況や楽天銀行の残高も1画面で見ることができとても見やすいです。
SBI証券はスマホで見ていると、急にパソコン表示用に切り替わるページがあり、見づらく戸惑うことがよくありました。
しかし、SBI証券でも2024年から「マルチデバイス対応」「見やすく使いやすいデザイン」を目標に掲げ、アップデートに注力しています。
最近ではスマホからでも、資産状況や買い注文もわかりやすい画面になってきていて、楽天証券に劣らない見やすさになってきています。
これからもアップデートを重ねて、使いやすくなることを期待をしています。
NISA投資でもらえるポイントのネット証券比較表(主要5社)
| 証券会社 | クレジットカード つみたてポイント | 投資マイレージ (残高ポイント) |
|---|---|---|
| SBI証券 | 三井住友カード/Oliveで利用可。最大3%還元(プラチナプリファードなど上位カード) SBI証券 | 投信残高に応じ年率0.1〜0.2%のVポイント進呈、対象は月間平均保有額1,000万円超で0.2%までSBI証券 |
| 楽天証券 | 楽天カード決済により積立額の0.5〜2%、楽天キャッシュなら+0.5%も可楽天証券 楽天証券ゴールドオンライン | 「投信残高ポイントプログラム」対象ファンドでは残高に応じて年率0.017〜0.053%還元 楽天証券ゴールドオンライン |
| 松井証券 | JCBなどカードでの積立に対して最大1%程度 | ポイント還元制度あり(投信残高に応じ、最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」毎月要エントリー |
| 三菱UFJ eスマート証券 (旧auカブコム証券) | au PAYカードなどでクレカ積立対応、Pontaポイント還元あり(詳細条件応相談) | 月間平均保有残高に応じて最大0.24% |
| マネックス証券 | マネックスカードやdカードなどで積立可能、最大還元率約3.1%(カードによる) | 投信残高に応じ年率0.03〜0.26%程度のポイント還元あり(ファンドと金額により変動) |
各社のポイントプログラムをまとてめみましたが、かなり複雑ですね。
・クレジットカードつみたてポイント(クレカつみたて)
NISAのつみたて投資とクレジットカードを組み合わせたポイント還元。
カード券種(普通・ゴールドなど)で還元率が異なりますが、各社大差はないレベルです。
・投資マイレージ(残高ポイント)
投資信託の残高に応じて還元率が異なったり、銘柄によって還元率が設定されている。
楽天証券では対象ファンド(投資信託)が数銘柄に限定されています。
証券会社選びでポイントは優先項目ではありませんが、もらえることに越したことはありません。
私はSBI証券で三井住友のクレジットカードとの組み合わせで、つみたて投資をしています。
毎月のつみたて投資10万円で1,000ポイント、投資信託残高で600ポイント以上還元があります。
1年間で約2万ポイント還元があり、ウエル活で利用しています。
私のVポイントアプリのスクショです。
8月は投資マイレージとクレカつみたて合わせて1,600ポイント以上還元されました。

初心者が失敗しやすい証券会社の選び方

- 窓口ですすめられて口座開設したけど、商品数が少なく投資先が限定されてしまう
- なんとなく選んだ証券会社だけど、アプリが使いにくく、取引や確認が面倒
- ポイント還元条件が複雑で実質的に恩恵が少ない
失敗しない選び方としては「総合力の高い大手ネット証券」を選ぶことです。
NISA口座は1年に1回違う証券会社に変更できますが、手続きが面倒だったり、つみたての空白期間が発生したりします。
最初の口座開設で長く利用できる証券会社を選ぶのがポイントです。
その点も踏まえて筆者のおすすめは「SBI証券」「楽天証券」です。
おすすめポイント
・SBI証券
低コストで商品数が豊富。Vポイント活用や口座数も多く初心者にも安心。
NISAはもちろん将来的な個別株、IPO取引もネット証券のなかでは定評があります。
・楽天証券
操作性と見やすさに定評があり、ポイントも充実。初心者でも迷わず取引できる安心感が魅力。
楽天グループのサービス・楽天経済圏との相性抜群。
まとめ
NISAを始めたいのに、証券会社選びで足踏みしていませんか?
最初の一歩でつまずくと、使いづらいアプリや少ない商品数などで後悔する人も少なくありません。
だからこそ「総合力の高い大手ネット証券」を選ぶことが、安心して長期の資産形成を続けるための最重要ポイントです。
今回ご紹介したSBI証券と楽天証券は、口座数・取扱商品・手数料・ポイント制度、どれを取っても業界トップクラス。
迷ったらSBI証券をおすすめします。
初心者でも迷わず始められ、長期投資でも安心して使い続けられます。
悩む時間はもったいない。
今こそNISA口座を開設して、1日でもはやく資産形成をしていきましょう。